2024年2月、千葉県が「週休3日制」を導入する方針を固めたことを発表し、話題になっています。
正確にいうと、勤務時間を別の日に割り振ることで「週休3日制」も可能になるフレックスタイム制の導入です。
働き方改革が叫ばれている昨今ですが、憧れの「週休3日制」を導入している企業にはどのような所があり、国が義務化するのはいつになるのでしょうか?
また、週休3日制にすることによって浮かび上がるメリットやデメリットにはどういったものがあるのでしょうか?
【週休3日制】で働きたい!
「今週もう一日休みがあればいいのに…。」誰もが一度は思ったことがあるのではないでしょうか。
私も以前働いていた会社が辛すぎて毎日このように思っていましたが、同時にありえないだろうとも思っていました。それが今後現実になる可能性はあるのでしょうか?
この記事では
・週休3日制とは ・千葉県の週休3日制開始はいつからなのか ・いつから義務化される?義務化の可能性 ・導入するメリットとデメリット ・全国で導入している企業や団体一覧
についてまとめましたので参考にして下さい。
【週休3日制】とは?

「週休3日制」とは、その名の通り1週間に3日間休める働き方のことで、「働き方改革」の一環として政府が推し進めている施策です。
現時点では週休3日制は義務化されていませんが、自主的な導入や、試験的な導入をする企業も増えてきています。
柔軟な働き方ができる一方で、給与が減額になる場合や、出勤日への負担のしわ寄せなど、デメリットも想定されます。
▼週休3日制の働き方には、大きく3つのタイプがあります。
総労働時間維持型
一週間で何時間勤務する、一ヶ月で何時間勤務する、といった労働時間の縛りはそのまま維持される制度です。
休みをとる一日分の勤務時間を他の出勤日の勤務時間に振り分けることで、週休3日制を可能とします。
給与や労働時間が週休2日の時と変わらない働き方です。
表向きには週休2日のときと給与は変わりませんが、1日の勤務時間が長くなるため、残業はあまりできなくなります。残業時間の収入が減り、トータルでの収入が減る可能性があります。
今回週休3日制の導入を発表した千葉県も、この「総労働時間維持型」になります。
給与減額型
一日分の勤務時間を減らす分、それに伴って給与も減額する制度です。
総労働時間維持型と違い、他の日に仕事をすることができないという点では柔軟性がないといえます。
給料が減ってでも家族との時間をたくさん過ごしたい、趣味のため定期的に平日の休みが必要…など、自身の家庭やプライベートに時間を使うことができる一方で、単純に働かない分収入が減るデメリットがあります。
給与維持型
給与維持型は、従来通りの給与を維持したまま週3日間の休みが適用される働き方です。
労働時間は一日少なくなるにもかかわらず給与は週休2日の水準が維持されるということは、勤務時間が減っても週休2日のときと同じ仕事量を求められるということです。
企業にとっては、人件費は変わらない一方で生産量は下がることが予想されます。また週休3日を維持するために他の日の残業が増え、残業代の支出が増えることも予想されます。
この給与維持型の制度を導入するのは、現状ではなかなか難しいのではないでしょうか。
【週休3日制】千葉県の導入開始はいつ?
千葉県(千葉県庁)が、職員の多様で柔軟な働き方を一層推進するため、2024年6月1日よりフレックスタイム制を導入する方針を固めました。
1日の勤務のうち、午前10時〜午後3時を「必ず勤務すべき時間帯」とし、残りの勤務時間を柔軟に割り振ることで、週休3日にすることも可能とのこと。週休3日の型でいうと「総労働時間維持型」となります。
2月14日に開会した定例県議会に、関連条例の改正案を提出したとのこと。
改正条例案の施行日は2024年6月1日。6月から、自分次第で週休3日の週を作ることができるようになります。とても羨ましいです!
【週休3日制】日本ではいつから義務化される?義務化の可能性

現時点では、条件を設けて従業員の希望により対応している企業が多く、全社で完全に週休3日以上を設定している企業はまだまだ少ないのが現状です。
また、例えば学校関連など、職種によっては週休3日制にするのは難しいところもあります。
▼厚生労働省の調査によると、令和2年からの導入率は以下の通り
令和2年度 8.3% 令和3年度 8.5% 令和4年度 8.6%
試験的な導入や条件付きを含めても、導入企業は1割未満。
しかし現在日本は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
働きやすい環境を整え離職率を下げ、様々な立場の人に働くチャンスを与えなければ、労働力が足りなくなってしまうんですね。
2021年4月5日、加藤勝信官房長官は週休3日制の導入について記者会見で以下のように発言されました。
「育児や介護、闘病など生活と仕事を両立させる観点からも多様な働き方の推進が重要だ」「政府として何ができるのか検討していく」
現時点ではすぐにでも週休3日制を義務化しようとする動きは見られませんが、今後年数をかけて、国として義務化を進めていく可能性は十分あると考えられます。
【週休3日制】のメリット・デメリット
週休3日制のメリットとデメリットには、このようなものがあげられます。
メリット ・プライベートの充実 ・ストレスの分散 ・効率よく時間を使うことができる ・子育て中の人や介護中の人、外国人など、さまざまな立場・状況の人に労働のチャンスが増える
デメリット ・労務管理が複雑になり労務を担う部署に負担がかかる ・これまでより給与が減る場合もある ・働き方によっては一日の労働負担が増加し、仕事の疲労が蓄積する ・週休3日制は、職種や立場によっては適用が困難な場合がある ・営業職などで、コンスタンスに顧客とのやりとりが発生する場合、不便や誤解が生じる ・職員同士の情報共有やコミュニケーションの機会が減る
メリットももちろんありますが、避けられないデメリットも多くあり、各企業の週休3日制導入を阻んでいます。
【週休3日制】導入企業一覧(全国)
パナソニックホールディングス
日本の大手企業で初めて完全週休2日制を導入した企業としても知られています。2023年2月には週休3日、週休4日を選べる勤務制度を一部の部署や雇用形態で導入しました。
佐川急便株式会社
忙しいイメージがある業界ですが、2017年から一部の営業所で変形労働時間制を導入して、1日の労働時間を10時間にすることで、週休3日を実現しています。基本的には月9日の休みがあり、育児・介護休業制度も充実しています。
ユニクロ
佐川急便と同じく、変形労働時間制を用いた1日10時間×4日勤務のフルタイム契約となり、週休3日でありながらも給与は変わりません。小売業界では珍しく週休3日制を導入している代表的な企業です。
SOMPOひまわり生命
仕事と育児・介護の両立を支援することを目的に、希望者は週休3日制を選択できます。勤務時間に変更はない代わりに、給与は2割ほど低く設定されています。
Zホールディングス(ヤフー)
土日の休日に加え1週当たり1日の休暇を取得できる週休3日制を取り入れています。この制度は、小学生以下の同居の子を養育する正社員および契約社員、家族の介護や看護をする正社員および契約社員のみ利用可能です。
日本マイクロソフト
2019年の8月から、実験的に週休3日制を取り入れました。非常に柔軟な働き方を提案しており、労働時間や勤務場所などを自由に決めることができます。
ファミリーマート
2017年から週休3日制も選択できるようになりました。全社で多様な働き方に対応しており、社有車による保育園所への送迎など、育児・介護と仕事の両立にも力を入れている企業です。
味の素
2018年から、60~65歳の再雇用社員を対象に、土日に水曜日を加えた完全週休3日制を採用しています。
リクルート
「週休約3日制」を継続しており、有給休暇などを除いても年間休日は145日です。柔軟な働き方を取り入れ、年間労働時間も給与も以前と同じ水準を保っています。
スカイマーク
新型コロナウイルス問題による需要の落ち込みに対処するため、2021年に週休3日制を導入しました。
日立製作所
2022年度に総労働時間も給与も維持したうえで週休3日にできる勤務制度を導入しています。
【週休4日制】を導入している企業
みずほフィナンシャルグループ
三大メガバンクのなかで初めて週休3日制、週休4日制を一部の部署で試験的に導入しています。休みが増えるぶん給与が減る「給与減額型」の勤務制度で、週休3日の場合は従来の約8割、週休4日の場合は約6割となります。
まとめ
週休3日制は政府が推し進める施策の1つではありますが、まだ義務化はされておらず一部の企業でのみ導入されているのが現状です。導入している企業も「試験的な導入」がほとんどで、本格導入している企業は稀のようです。
企業としても、導入にあたり従業員全員を週休3日にするのか、または希望者のみにするのか等、様々な方法の中から、それぞれのリスクを踏まえて決断しなければなりません。
週休3日制の導入を待つばかりでなく、上司からの有休取得の斡旋や、上の人がどんどん休みを取って休みやすい雰囲気を作るなど、身近なところからも働きやすさを作っていきたいですね!






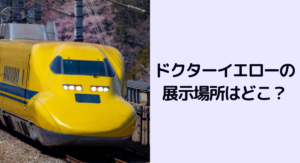
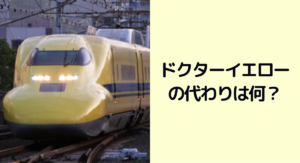
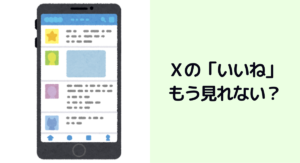
コメント